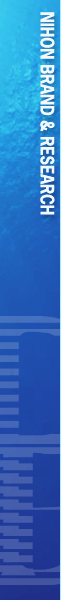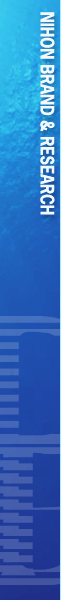■「輸出」の実施規定への追加 (平成19年1月1日 施行)
かねてより問題になっていた、模倣品の輸出行為についての法改正が行われました。特許法、
実用新案法及び意匠法の「実施」の定義、商標法の「使用」の定義に「輸出」が加えられたのです。知財の保護はどの企業においても重要な課題ですから、これは朗報といえるでしょう。
POINT: 特許法、実用新案法及び意匠法の「実施」ならびに商標法の「使用」の定義に「輸出」が
加えられました。
これにより、模倣品の輸出行為を水際で差し止め等を行うことを可能となります。
■譲渡等を目的とした所持の間接侵害規定への追加 (平成19年1月1日 施行)
侵害物品の譲渡等(譲渡、貸渡し、輸出)を目的としてこれを所持する行為が、間接侵害規定
(みなし侵害規定)に追加されました。(商標法では既に商標法37条2号で規定済みです。)
POINT: 従来、侵害物品の所持行為は侵害とされていませんでした。従って、所持行為を発見した場合に、その差し止めを請求するためには、譲渡などの真実またはその恐れを立証する必要がありました。しかし、改正後は、侵害物品譲渡、貸渡し、輸出を目的としてこれを所持する行為が、間接侵害に該当することとなります。
つまり、これにより、譲渡などによって侵害物品が拡散する前段階である所持の段階における取り締まりが可能となり、権利の侵害防止の実効性が確保される事になりました。今までヤキモキしていた企業にとっては、待ち望んでいた法改正と言えるでしょう。
■刑事罰の強化 (平成19年1月1日 施行)
産業財産権の侵害罪に係る量刑を引き上げると供に、法人重課に係る罰金額の上限を引き上げる等、刑事罰が強化されることになりました。
POINT: 特許権、意匠権及び商標権の直接侵害に対する懲役刑の上限が5年(意匠は3年)からを10年に、罰金額の上限が500万円(意匠は300万円)から1,000万円に引き上げられました。 実用新案権の侵害罪に係る懲役刑の上限が3年から5年に、罰金刑の上限が300万円から500万円に引き上げられました。 間接侵害については、産業財産権四法ともに懲役5年とし、罰金刑は500万円となりました。 四法統一的に懲役刑と罰金額の併科が導入され、法人重課については、罰金刑1億5千万円以下から3億円以下に引き上げられました。 |